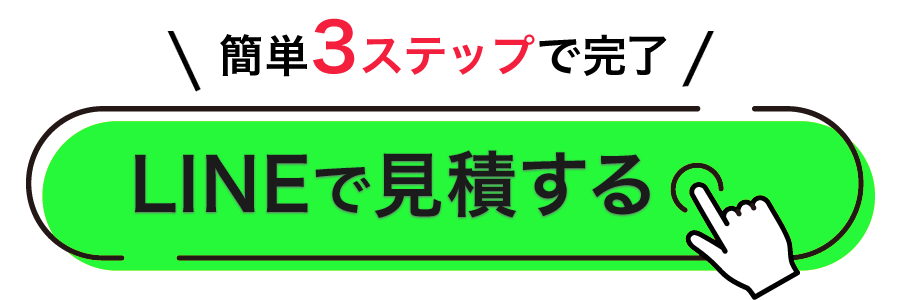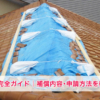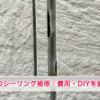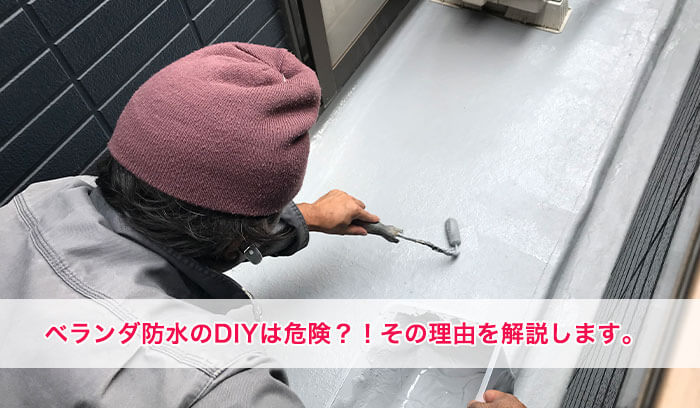ベランダからの雨漏り応急処置5選!今すぐできる対処法と費用の目安を紹介!

雨漏りを見つけたとき「どこから水が入った?」「どうすれば止まるの?」と焦りますよね。
放置すると室内や下階、隣家まで被害が広がることがあるので、早めの対応が大切です。
雨漏りは自然に直ることはなく、放っておくとどんどん悪化してしまいます。
今回の記事では、"自分でできる応急処置の方法“や雨漏りの原因と発生しやすい場所などを紹介!
また、応急処置では直らないケースや修理の費用相場まで分かりやすく解説します。
すでに雨漏りしている場合は、被害を広げないために、"今すぐできる対応“をチェックしてみてください。
ベランダの雨漏りを放置すると危険!起こりやすいトラブル
ベランダの雨漏りを放置すると、見えない部分の下地材や構造が劣化し、結果的に修繕費用が高額になることもあります。
ここでは、雨漏りを放置した際に起こりやすい代表的なトラブルを紹介します。
室内への浸水や天井のシミ

ベランダの床や防水層にできたわずかな隙間から水が入ると、室内の天井や壁紙にシミが発生します。
放置すると湿気がこもり、カビや臭いの原因になることがあります。
見た目が悪くなるだけでなく、下地の木材が腐食して構造に影響を与えることもあるため、早めの対応が重要です。
下階や隣家への水漏れトラブル

ベランダの排水が詰まったり防水層が破れたりすると、階下の天井や隣家の外壁にまで水が流れ込むことがあります。
自分の家だけでなく、他人の住まいに被害が及ぶと、修理費や補償のトラブルに発展するケースもあります。
特に集合住宅では、雨漏りの被害範囲が広がりやすいので注意が必要です。
建物の劣化・カビ・腐食

雨漏りを放置すると、コンクリートや木材など建物の主要部分が長期間湿った状態になります。
湿気によって鉄筋が錆びたり、木材が腐ったりして、建物全体の耐久性が低下してしまいます。
さらにカビが発生すると、健康への悪影響も考えられるため、早めの対処が欠かせません。
今すぐできる!ベランダ雨漏りの応急処置
ベランダで雨漏りを見つけたら、まずは「応急処置」で被害を最小限に抑えましょう。
すぐにできる対応をしておくことで、室内や下階への浸水を防ぎ、修理時の費用負担も減らすことができます。
まずは安全を確保

雨漏りが起きているときは、滑りやすく転倒の危険があります。
まずは、安全を最優先に行動しましょう。
感電のリスクを避けるため、電気製品や延長コードなどを近づけないようにします。
また、屋外での作業は、雨風が強いときは中止して、天候が落ち着いてから行うのが安全です。
溜まった水をバケツや雑巾で除去

ベランダに水が溜まっている場合は、バケツや雑巾を使ってできるだけ水を取り除きましょう。
排水がうまくいかないと、床の隙間から水が内部に浸み込み、被害が広がってしまいます。
防水層を傷つけないように、優しく手作業で除去するのがポイントです。
排水口(ドレン)の詰まりを取り除く

雨漏りの原因で多いのが、落ち葉やゴミによる排水口(ドレン)の詰まりです。
ゴミや泥を取り除き、水がスムーズに流れるようにしましょう。
排水口の奥が詰まっている場合は、無理に押し込まず、ワイヤーブラシや細い棒などでやさしく掃除します。
水が流れるようになれば、雨水の逆流による雨漏りの悪化を防げます。
ブルーシートや防水テープで一時的にカバー

雨漏り箇所が特定できたら、ブルーシートをかぶせたり、防水テープで一時的にふさいでおきましょう。
ブルーシートは風で飛ばされないように、レンガや重りなどでしっかり固定します。
防水テープを使う際は、貼る前に水分を拭き取り、乾いた状態で密着させることが大切です。
これはあくまで「一時的な対応」なので、早めに業者へ連絡しましょう。
作業前後の写真を撮っておく

応急処置を行う前後の状態を、「撮影」しておくことも重要です。
破損箇所や雨漏りの様子を記録しておくことで、修理業者への説明がスムーズになります。
また、台風や大雨など自然災害が原因の場合は、火災保険の申請時にも証拠として活用できます。
火災保険について、こちらの記事で詳しく解説しています!
やってはいけないNG応急処置

突然の雨漏りに焦って対応すると、かえって被害を広げてしまうこともあります。
「これで大丈夫!」と思って行った行動が、防水層を傷つけたり、排水を妨げる原因に・・・
ここでは、絶対に避けたいNGな応急処置を紹介します。
コーキング材をむやみに塗る
雨漏り箇所にコーキング材を無理に塗り込むと、かえって水の逃げ道を塞いでしまうことがあります。
一時的にとまって見えても、内部に水が溜まっていたり、見えない部分で腐食やカビが進行する危険があります。
排水口(ドレン)を塞ぐ
「水の流れを止めれば雨漏りも止まる」と思って、排水口(ドレン)をテープやコーキング材でふさぐのもNGです。
排水ができなくなり、水が溢れて、別の箇所から浸水してしまうことがあります。
雨の中、無理に作業する
雨の中での作業は非常に危険です。
足元が滑りやすく、転倒や関電などに事故につながる恐れがあります。
雨漏りの主な原因と発生しやすい場所
ベランダの雨漏りは、「経年劣化」や「施工不良」など、いくつかの要因が重なって起こることが多いです。
ここでは、特に”トラブルが起きやすい箇所“と"原因“を紹介します。
防水層の劣化

ベランダの床面には、雨水を建物内部に染み込ませないために「防水層」があります。
紫外線や雨風の影響、摩擦によって経年劣化し、ひび割れや膨れが生じると、そこから雨水が侵入してしまいます。
排水口(ドレン)の詰まり

ベランダの排水溝(ドレン)が、落ち葉やゴミで詰まると雨水が行き場を失い、床に溜まってしまいます。
その状態が続くと、水圧で防水層の隙間から雨水が入り込み、雨漏りを引き起こします。
特に、秋~冬にかけて落ち葉が多く詰まりやすいため、定期的な清掃が欠かせません。
シーリング・サッシのひび割れ

シリングやサッシの周辺に小さなひびや隙間ができると、そこから雨水が侵入します。
雨漏りの原因は「床」と思いがちですが、実は"サッシまわりの劣化“が原因の場合も多くあります。
エアコンの配管や笠木(手すり)の隙間

エアコンの配管まわりやベランダの笠木(手すり)部分の隙間も雨水の侵入口になりやすい部分です。
配管のパテが劣化すると、小さな穴から雨水が入り込み、壁内部に浸透してしまいます。
また、笠木(手すり)の継ぎ目部分も、コーキング材の劣化や亀裂があると水が流れ込みやすいため注意が必要です。
応急処置では直らないケース

応急処置で一時的に雨漏りが止まっても、原因が解決していなければ再発してしまいます。
見た目では直ったように見えても、内部は既に水が回っていることもあるためとても危険な状態です。
防水層が剥がれている
ベランダ床の防水層の表面が浮いていたり、部分的に剥がれている場合は、応急処置では対応できません。
剥がれた箇所から常に水が入り込み、下地まで劣化が進んでしまいます。
防水層が劣化している場合は、トップコートの塗り替えや防水層の再施工など、大規模な工事が必要になります。
室内まで浸水している
すでに室内に水が染み込んで、天井や壁にシミがある場合、内部構造にまで被害が及んでいる可能性が高いです。
修理をせずに放置すると、木材の腐食やカビの原因になり、修理費用が大きく膨らみます。
早急に業者へ連絡し、浸水経路の特定と補修を依頼しましょう。
何度も再発している
雨漏りを何度も繰り返している場合、原因の特定が誤っている可能性があります。
表面的にコーキングやテープでふさいでも、内部の構造部分に問題が残っていると、根本的解決になりません。
繰り返す雨漏りは、建物全体の耐久性にも影響するため、専門業者に正しい調査を依頼するのが安心です。
こちらの記事で「当社が行っている雨漏り調査」を詳しく紹介しています。
“雨漏りに悩んでいる人"や"雨漏り調査って何をするんだろう?"と気になる人は、ぜひご覧ください!
ベランダ雨漏り修理の費用相場と保険の利用

雨漏り修理の費用は、原因や被害の範囲によって大きく変わります。
軽度であれば補修で済む場合もありますが、防水層の再施工や下地の張り替えが必要な場合は、費用も高くなります。
| 原因・工事内容 | 費用相場の目安 |
|---|---|
| 排水口の詰まり掃除 | 1~3万円 |
| コーキング補修 | 5,000~20,000円(1箇所あたり) |
| トップコート塗り替え | 100,000円~ |
| 防水層の再施工 | 300,000円~ |
火災保険で費用をカバーできるケースも!

台風や大雨など、自然災害が原因の雨漏りであれば、火災保険で修理費用が補償される場合があります。
保険会社に申請する際は、「被害箇所の写真」や「発生日時のメモ」などを残しておくとスムーズです。
ただし、経年劣化や施工不良による雨漏りは"対象外“になるため、申請前に業者に相談すると安心です。
火災保険について、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください!
まとめ
ベランダの雨漏りは、放置することで室内への浸水や建物の劣化、近隣トラブルにつながる恐れがあります。
小さな水漏れでも、早めに応急処置をして原因を特定することが大切です。
- 雨漏りは自然に直ることはないため、早めの対応が被害を最小限にするポイント!
- 応急処置では「安全確保」と「排水の確保」が最優先
- コーキング材をむやみに使ったり、ドレンを塞ぐのはNG!
- 防水層の劣化や繰り返す雨漏りは、専門業者による修理が必要
- 修理費用は、広さと規模・工事内容により大きく異なる
- 経年劣化ではなく自然災害が原因の場合、火災保険が使えるケースも◎